臍帯血は「万が一のために保管しておきたい」と考える方も多い一方で、「実際に使えるの?」「使えなかったらもったいないのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
ここでは、臍帯血バンクのデメリットや実際の使用件数・使用できなかった例について、わかりやすくまとめました。
臍帯血保存の主なデメリット
臍帯血には医療的価値がある一方で、現時点では以下のようなデメリットもあります。
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| 使用機会が非常に少ない | 保管しても、実際に使用する確率は約0.3%程度と言われています。 |
| 白血病など一部の病気には使えない | 自分の臍帯血には異常細胞が含まれる可能性があるため、自己利用が不適なケースも。 |
| 費用が高額 | 民間バンクでは初期費用15〜20万円、保管料も毎年1〜2万円程度かかります。 |
| 採取できない場合がある | 分娩状況によっては、十分な臍帯血が取れず保存できないこともあります。 |
| すべての病院で対応しているわけではない | 対応していない産院もあり、事前確認が必須です。 |
民間バンクでの実際の使用件数
民間臍帯血バンク最大手「ステムセル研究所」の公表データによると、
- 累計保管件数:約17万件以上(2023年時点)
- 実際の使用件数:約500件(移植・研究利用含む)
使用された割合は約0.3%前後。
つまり、保管しても99%以上のケースで使われていないのが現状です。
使用できなかった主な理由
臍帯血を保管していても、以下のような理由で実際には使用できないケースがあります。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 白血病などでは自己血は使えない | 自身の異常細胞を含む可能性があり、他人の血液が優先されることが多い。 |
| 医師の判断で不要とされた | 治療方針や医学的適応によって使用しないことも。 |
| 幹細胞数が足りなかった | 治療に必要な量を満たさなかった。 |
| 病気が適応外だった | 期待されていた疾患(自閉症や脳性麻痺など)が研究段階で、臨床使用ができなかった。 |
実際の体験談(一部紹介)
- 「脳性麻痺の子どものために保管したけれど、研究段階でしか使えないと言われた」
- 「白血病を発症し保管していた臍帯血を希望したが、自己血は使えないと説明された」
- 「保管していて使っていないけど、安心感はあるから後悔はしていない」
まとめ:臍帯血の保存は「安心料」と考えるかどうか
臍帯血の保存は、現状では使う機会が非常に限られているのが実情です。ただし、再生医療や臨床研究の進歩により、将来的に使える病気が広がる可能性はあります。
したがって、
- 「今すぐ使うことは少ない」と理解したうえで、将来への保険として保存したいか?
- 費用に対して納得できるか?
を夫婦でよく話し合うことが大切です。


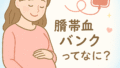
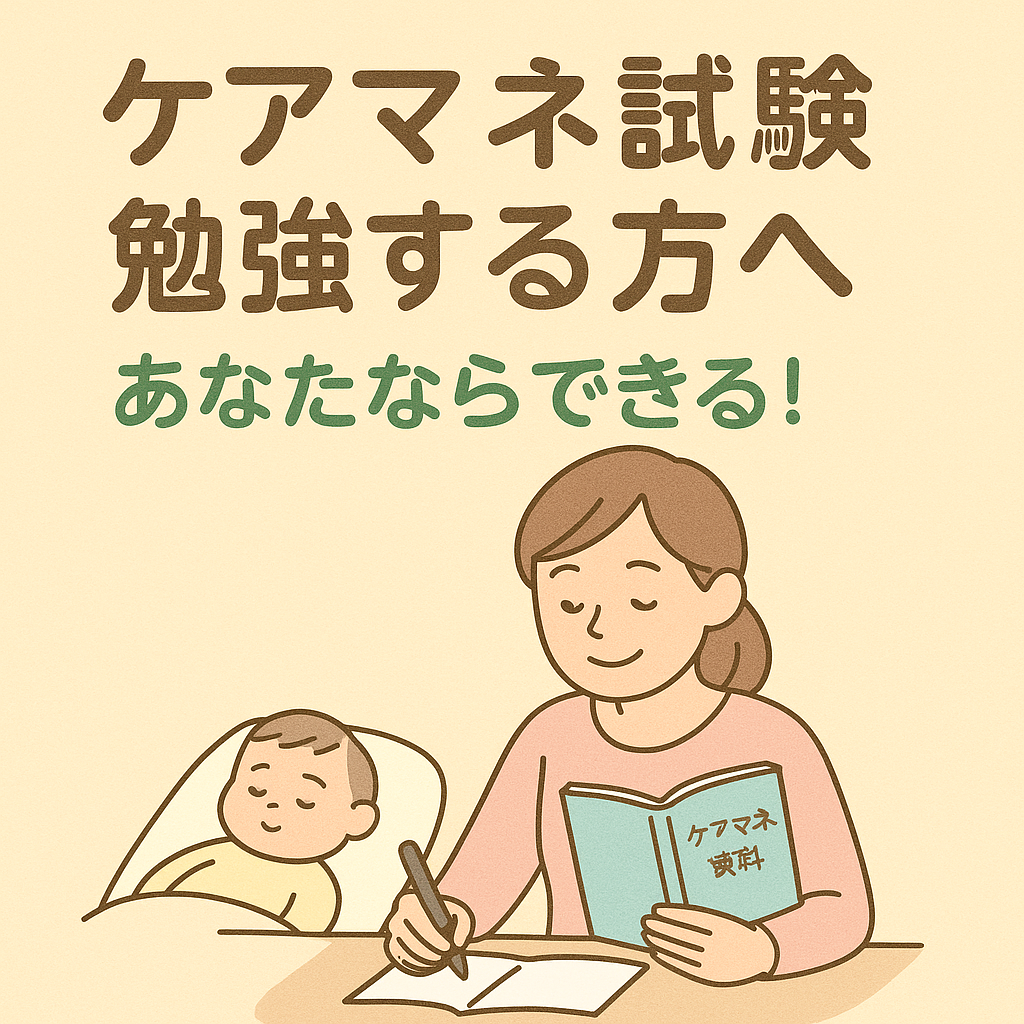
コメント